令和6年度ピア学びの講座
日 時:令和7年1月11日(土)10:00~12:00
場 所:多目的ルーム
講 師:青木 裕史 氏
参加者:8名
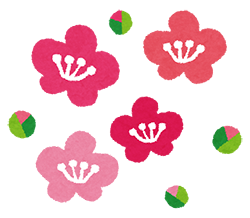
今回はテーマ「ピアサポーターとして 人との支え合いで見えてきたこと」のもと、講師に佐賀県佐賀市在住でピアサポーターの青木裕史氏をお招きし講座を開催しました。
青木氏は、福岡県久留米市のオープンスペースでピア職員・法人理事として6年間勤務され、併せて、佐賀県佐賀市の地域活動支援センターでピアサポーターとしても4年間働かれています。
そのお仕事の中で「その人の主体性を大切にした関係づくり」「お互いの経験を介しての関わり」に重きを置いて、精神や発達に障害がある方と関わっておられます。
まずは、自己紹介とともに自身を幼少期より振り返り、10代の頃は自らの考えで行動するというより、他人の考えが優れていると考えて、聞いて正解と思われることを実行していたことや高2で初めてできた親友が数年後他界し、亡き親友の意思を受け継ぎSE(システムエンジニア)になったことなどを語られました。
友人の夢を叶えるためになったSEの仕事は激務で、病気を発症してしまい、精神科病院に入院したり、デイケアに通いながら、病院と家族の管理下に置かれて、何が正解なのかわからず、自分の主体性がなかったことから、毎日「本当の自分を探す」という思いを胸に20代から30代を過ごされたそうです。
人生を大きく変えたのは、「WRAP(元気回復行動プラン)」「ピアサポート」「共同想像」という活動や概念に出会ったことで、2015年よりピアサポーターとして活動を始めて、ACT(包括型地域生活支援プログラム)・B型事業所・リカバリーカレッジなどに勤務した後現職に就かれています。
30代にピアサポーターに継続的に対話を行いながら、「迷う自分を認めて受け入れてもらえた体験」や「ロールモデル」がみつかったことで、ピアサポートの大切さを知り、専門職チームの中で、「自分を認め、できることを増やすこと」で自分しかできないことを発見していったそうです。
そんな経験をもとに、青木氏自身は「ピアサポートする時、自身の経験や性質・捉え方をもとに人と接しているが、それを受け入れるピアの声から、青木氏自身のことを知り自分が形づくられる過程にあるのだと考えています」と話されていました。
最後に、「人との支え合いの中で見えてきたこと」は、問題解決をしない関係性づくり・ピアの話を受け止め認めることで、ピアの望むことを一緒に取り組むことで「受容と方向性」が大切だと気づき、ピアサポーターとピアお互いの偽りのなさを大切にして、双方向で誠実な関係づくりをすることや関係性に責任を持ち、お互いの価値観や物事の捉え方を理解する機会が重要だとお話してくださいました。
参加者からは、
『「待つことの大切さ」疾患があるとか関係なく人として相手と接することの大切さを感じました』や
「ピア本来の意味について改めて考えさせられました。相手を尊重し、自分を大切にして、一方通行にならず、ただ待つということが大事だと気づかされました」
などの感想をいただきました。
